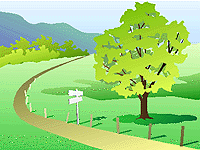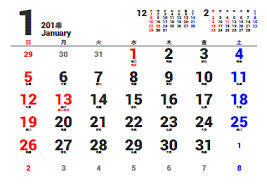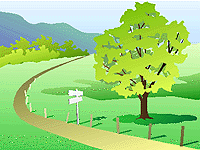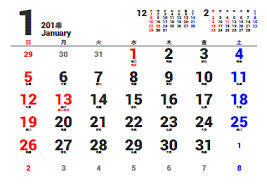| ”汁もの”のレシピ |
|
あおさ汁
(三重県) |
 |
 ♪材料 ♪材料
①あおさ・・・5g
②だし汁・・・3カップ
③味噌・・・大さじ3 |
| 『あおさ』は、ヒトエグサのことを方言で表した言葉です一般的には『あおさ』または『あおさのり』と呼びます、ヒトエグサは主に佃煮の原料として使われる海苔の一種で、養殖が始まったのは、伊勢湾、三河湾の一部で1930年頃からといわれています。ヒトエグサの採取時期は1月から5月にかけて数回に分けて行います。 |
 ♪下拵え ♪下拵え
①あおさはさっと水で戻します。 |
♪作り方
①だし汁を煮立たせ、味噌を溶き入れてひと煮立ちさせます。
②水気をしぼったあおさを加えてすぐ火を止めます。
*注意⇒あおさは煮すぎると香りが飛び、色も悪くなります。 |
| |
打ち豆沖汁
(滋賀県) |
 |
 ♪材料 ♪材料
①大豆・・・80g
②里いも・・・2コ
③油揚げ・・・1/2枚
④干しずいき・・・1/2本
⑤青ねぎ・・・1/2本
⑥豆腐・・・1/3丁
⑦煮だし汁・・・カップ4杯
⑧みそ・・・大さじ4杯 |
打ち豆汁は、炊いた大豆を打って潰したものと野菜を炊いた汁物です。
栄養満点でやさしい味わいです |
 ♪下拵え ♪下拵え
①大豆を洗い水に浸して、ひと晩おきます。
柔らかくなるまで煮れば、水をきってすりこぎで豆を
あらくつぶします。
②里いもは皮をむいて適当な大きさに切ります。
③油揚げは熱湯をかけて油抜きをし、短冊切りにします。
④ずいきは水でもどした後、適当な長さに切ります。
⑤青ねぎは小口切りにしておきます。 |
♪作り方
①煮だし汁に大豆とみそ半量を加えて、弱火で煮ておきます。
②里いもとずいきを加えて煮て、
柔らかくなったら豆腐と残りのみそを加えて、ひと煮立ちさせます。
③器に盛って青ねぎを散らして出来上がりです。
|
| |
|
|
飛鳥汁
(奈良県) |
|
 ♪材料 ♪材料
①鶏肉・・・15g
②清酒・・・0.5g
③はくさい・・・40g
④にんじん・・・10g
⑤しゅんぎく・・・15g
⑥えのきだけ・・・5g
⑦ささがきごぼう・・・5g
⑧豆腐・・・30g ⑨うるめ節・・・2g
⑩だしこんぶ・・・0.5g
⑪しょうゆ・・・0.5g
⑫みそ・・・7g
⑬白みそ・・・2g
⑭牛乳・・・30g
⑮水・・・60g |
| 鶏肉を牛乳で煮て食べる鍋物で、飛鳥汁は古くから飛鳥地方に伝わる家庭の鍋料理です。牛乳と鶏肉がほどよく調味された味は、すきやきや水たきでは味わえないもので野菜にもよい味がつき、特にスープが美味しくなります |
 ♪下拵え ♪下拵え
①鶏肉は小口切りにし、清酒をふりかけておきます。
②はくさいは大きめに切ります、
③にんじんはいちょう切りにします、
④ しゅんぎく、えのきだけは2~3cmに切ります。
⑤ごぼうは酢水につけ、あく抜きをします。
⑥豆腐はさいころ切りにします。 |
♪作り方
①うるめ節とだしこんぶでだしをとり、
煮えにくいものから入れて、煮ます。
②材料がやわらかくなれば、しょうゆ、みそで味をととのえ、
最後に牛乳としゅんぎくを加えてしあげて出来上がりです。 |
| |
|
|
船場汁
(大阪府) |
 |
 ♪材料(4人分) ♪材料(4人分)
①サバ・・・1尾
②大根・・・8cm
③白ねぎ・・・1本
④ゆず・・・適量
⑤昆布だし・・・カップ3杯
⑥酒・・・大さじ2杯
⑦塩・・・小さじ2/3杯
⑧うすくちしょう油・・・小さじ1/2杯 |
| 大阪の船場の商屋でよく食べられていた料理。もともとは焼いて食べたあとの塩サバのあらでだしをとり、大根を加えたもの。 |
 ♪下拵え ♪下拵え
①白ねぎは細切りにして水にさらしておきます。
②ゆずは皮を細切りにします。
③サバは3枚おろしにして血合い骨を抜き、片身を半分に切ります。
④ざるにあげて軽く塩をし、しばらくおきます。 |
♪作り方
①サバに熱湯をかけます。
②短冊切りの大根とサバを昆布だしで煮ます。
③塩で味つけをし、最後にうすくちしょう油を加えます。
しょう油を加えたら煮立てないようにします。
④器に盛って白ねぎと、ゆずの皮を細切りにした物を
のせて出来上がりです。 |
 |
 |
 |